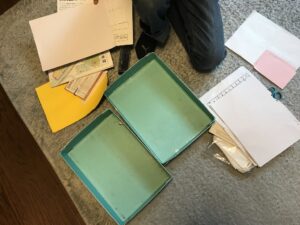片づけでは、「もの」の定位置を決めて、元へ戻すことが大切。
紛失を防ぎ、必要な時にすぐ出せるようにです。
もしも「戻せない」なら…
何か理由があるはず。
さらに片づけが苦手なら、なおさら「定位置」を決める必要がありますね。
定位置を決める時のポイント、戻せない場合の考えられる原因は様々。
その為、我が家でも悩ましい時があります。
特に片づけが苦手な長男にとっては、「定位置へ戻す」を習慣化するのも一苦労。
試行錯誤をしている、家の鍵の定位置についてです。
定位置を決めるとき
ものに決まった場所を与えることは、いわば「ものの住所が決まっている」ということ。
片づけでもよく言われます。
この定位置を決める時は、使う場所の近くが良いと考えます。
使う場所の側なら、すぐ使えて、すぐ戻すことが出来るからです。
その為、使う場所と、しまう場所が離れない方が良いとされます。
ただこの時、離れない方が良いとはいえ、考えたいのは「使う場所」
その場所が、「本来何をする場所なのか?」を明確にする必要があります。
例えば、ダイニングテーブル。
便利だからと色々な「もの」が集まったのなら。
食事スペースが狭くなり、逆に不便です。

- 何を目的とするのか?
- 何を優先したいのか?
考える必要はありますね。
戻せない原因が、どこにあるのか?
定位置を決めても、「戻せない」が発生した時。
何が原因か?考える必要があります。
考えられる原因は、
- 定位置の場所が適していない
- 戻す方法が面倒
- 定位置のスペースが狭い
- 定位置を忘れる
といった感じでしょうか。
定位置の場所が適していない
よくある原因としては、場所が適していないのではないか?ということ。
- 使う場所と、しまう場所が離れていないか?
- 高さは適しているか?
などチェックしてみることを、おすすめします。
また、その人にとって適していることが大切ですね。
戻す方法が面倒
蓋をしたり、目隠ししたり、奥まっていたり。
手間が多いと面倒になってしまいます。
また、中身が見えない収納用品や、扉の中へ入れてしまうと分からなくなることも。
隠す収納はやめて、パッと見て分かることも大切です。
定位置のスペースが狭い
収納は8割を心掛け、ゆとりがあることも大切です。
ぎゅうぎゅうになっていると、ものが重なって埋もれてしまいます。
特に、上からどんどん重ねてしまうと、下のものが死蔵品に。
そうならない為には、収納の場所に対し収納の仕方が適していることが重要です。
まずは、収納の中がパッと見て分かる量にしてみることを、おすすめします。
定位置を忘れる
なぜ忘れてしまうのか?が大切です。
- 場所が適していないから忘れてしまうのか?
- 習慣化が難しいのか?
場所が適していないから忘れてしまうのと、習慣化に時間がかかっているのでは対応が違うと考えています。
そもそも場所が適していないのなら、場所を変えれば出来るようになりますね。
習慣化が難しい場合は、工夫が必要。
記憶に頼らずに取り出せるよう、ラベルを貼る方法も効果的です。
「見える」ことが大切だったりしますね。
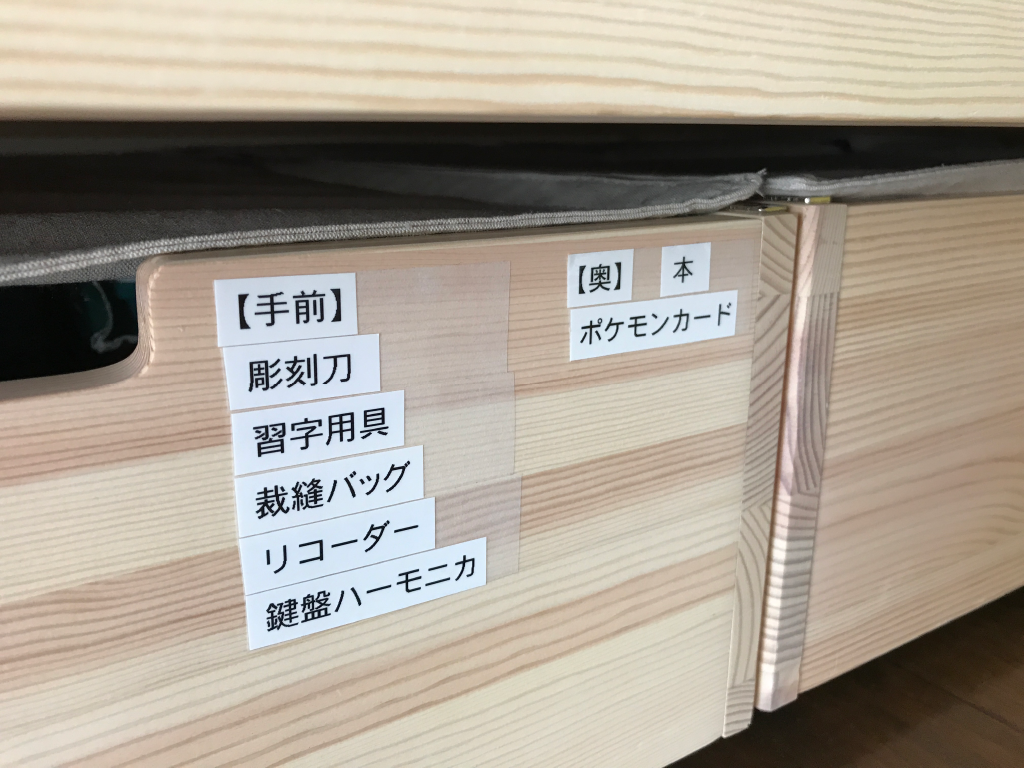
家の鍵の定位置
我が家の長男は、そもそも習慣化に時間がかかるタイプ。
寮生活から戻ってきた時に話し合い、家の鍵の定位置を、玄関の下駄箱の中に決めました。
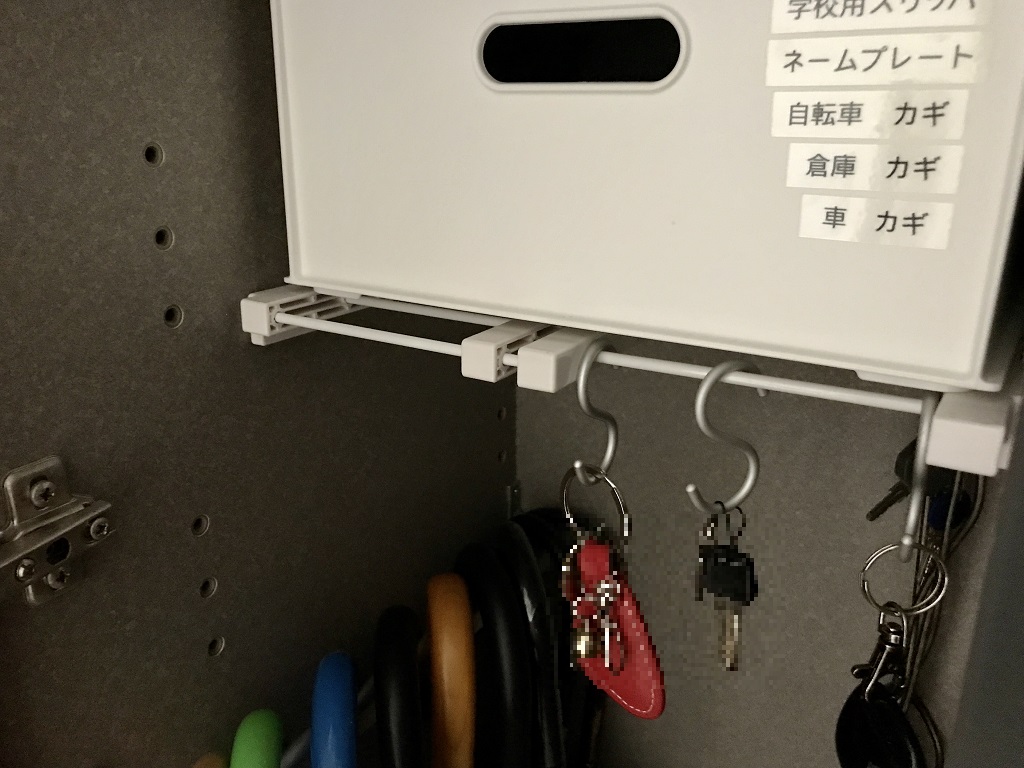
出掛ける時、サッと持ち出せるように。
靴の出し入れもするので忘れないし、便利。
ところが、「戻す」がなかなか出来ません。
家を出る時は、スムーズに持ち出せます。
ところが帰宅時。
鍵を開けて家に入った後、階段を上がった正面の部屋まで一直線。
持ってきてしまうのです。
大学から帰ったら、バイトから帰ったら、出掛けて帰ったら。
そのまま部屋の中、パソコンの机へ鍵を置いてしまう。
パソコンの机は広く、なくなる心配はあまりありません。
ですが次に出掛ける時、玄関で鍵を取ろうとすると…
もちろん無いので、靴を脱いで取りに戻ることに。
これは、玄関という場所が適していないのか?
と考えましたが、出掛ける時に取りに戻るのは面倒だから玄関が良いとのこと。
収納場所が扉の中なので、見えないから出来ないのか?
と考えましたが、防犯上、扉の中が良い。
結局、一番大事にしたいことは「鍵の場所がどちらに置いても決まっていること」となりました。
四角-scaled.jpg)
鍵が迷子にならなければ良し!
としました
そこで、つい持っていってしまう部屋にも、鍵の定位置を作ることに。
パソコンの机の横、タンスの上へブックエンドを逆さに置き、磁石付きフックを。


真っすぐ持って上がった時は、ここへ置くように。
こうして、定位置が2か所になりました。
彼が習慣化するまでは、様子見です。
習慣化を目指して
チェーンで鍵を、鞄に付ける方法も考えました。
確実な方法ですね。
ですが、使う鞄は3つ。
それぞれに付けると考えると…
時間がかかっても、定位置に戻す習慣を付ける方が良いのでは?
となりました。
定位置さえ決まっていれば、切り離して考えられます。
取りに戻る手間は、忘れた問題だと考えました。
出掛ける時に忘れるのか?戻す時に忘れるのか?
そう考えると、「玄関が便利」とは限らない。
忘れずに「ここ」から持ち出すことが出来れば、玄関ではなく「ここ」が適しているのかもしれません。


たとえ持って上がったとしても、そこにも定位置があれば探す必要はありません。
鍵が迷子にならなければ良しと受け止めることにしました。
困っていることは何?誰?
時と場合で、どちらに戻すかは本人任せ。
次第に場所が1か所になるかもしれないし、このまま2か所を行ったり来たりかもしれません。
本人は、取りに戻っても特に問題がないように見えます。
取りに戻ることが困り事、という訳ではないのかもしれないな~なんて思っています。
苦手をカバーする方法はいくつもありますが、どうしたいのか?という目的が大切なのだと思います。
最優先は、ものの迷子を無くすこと。
その為我が家では、このような方法となりました。
定位置を決める時、
- つい置いてしまう場所
- 最初に探す場所
なども良いと感じています。
「つい置いてしまう場所」→ その場所が楽・便利だから
「最初に探す場所」→ そこに置いたような気がする(場所の見当がつく)から
息子の場合も、つい置いてしまう場所が「定位置」なのかもしれません。
彼にとって、習慣化に時間がかかるのはよくあること。
苦手なことだと理解して、待つことも大切なのですよね…
苦手は苦手。
100%を目指さないことで、気持ちも楽に。
本人が困っていなければ良い!と考えれば、周りも楽に。
試行錯誤、上手くいかなければ変更可能なのが、片づけの楽しいところ。
一度で完璧を目指さず、実験感覚で最適な定位置を探してみるのも良いと思いますよ♪
※追記…2か月後(トータル3年半)、玄関で習慣化できました(笑)